数年前、私はある国家試験の合格を目指し、友人たちと勉強部屋に集まって一日中こもりきりの毎日を送っていました。
私たちのこれからの人生を左右する、あまりに過酷な試験。 独自の勉強法を作り上げ、朝から晩まで机にかじりつく日々。部屋の中には、常に「焦燥感」という名の、乾いた空気が流れていました。
そんなある日、一人の友人がコーヒーメーカーを、そしてもう一人の友人が「手挽きミル」を部屋に持ち込んできました。
「ゴリゴリ」という音が、合図だった
それまで私にとってのコーヒーは、眠気を覚ますための苦い液体でしかありませんでした。 けれど、友人がミルを回し始めたとき、私の常識は一変しました。
「ゴリ、ゴリ、ゴリ……」
静まり返った勉強部屋に響く、リズミカルな音。 そして、砕かれた豆から溢れ出してきたのは、これまで嗅いだことのないような、力強く、それでいてどこか華やかな香りでした。
「コーヒーって、こんなに鮮やかな香りがするものだったんだ」
その香りを吸い込んだ瞬間、試験のプレッシャーでガチガチに固まっていた思考のノイズが、スッと消えていくのがわかりました。
逆転してしまった、主従関係
あの香りの魔法にすっかり魅了されてしまった私は、すぐに自分でもミルを買い、自分なりに豆を調べ、淹れ方を研究し始めました。
「どうすれば、あの一杯をもっと美味しくできるか?」
気がつけば、勉強するためにコーヒーを飲むのか、コーヒーを飲むために勉強しているのか、どちらが主目的かわからなくなるほど、私たちの時間はコーヒーを中心に回り始めていました。
張り詰めた部屋でミルを回す音を合図に、仲間たちがふっと表情を緩める。 あの「コーヒー休憩」という儀式こそが、私たちが正気を保ち、最後まで走り抜くための唯一の光だったのだと今でも思います。
突き詰めるほどに感じた、ある「壁」
そうやって自分自身がどっぷりとコーヒーの世界に浸かり、仲間たちのために豆を選び、淹れ続ける役目になって気づいたことがあります。
あの日、友人が持ち込んでくれたあの感動を、もし他の誰かに伝えようとしたら? そう考えて調べれば調べるほど、私はある奇妙な感覚に陥りました。
自分がハマればハマるほど、その世界がどんどん「難解で、閉じた場所」に見えてきたのです。
「コーヒーの世界って、なんでこんなに難しい言葉ばかりで、入り口が高いんだろう?」
あんなに自由で、あんなに心を救ってくれた一杯のはずなのに、いざ知ろうとすると途端に高い壁が現れる。その違和感が、今の私の活動の種になっています。
次回は、私が初心者の頃に感じた、この「コーヒー界の入り口の高さ」についてお話しします。

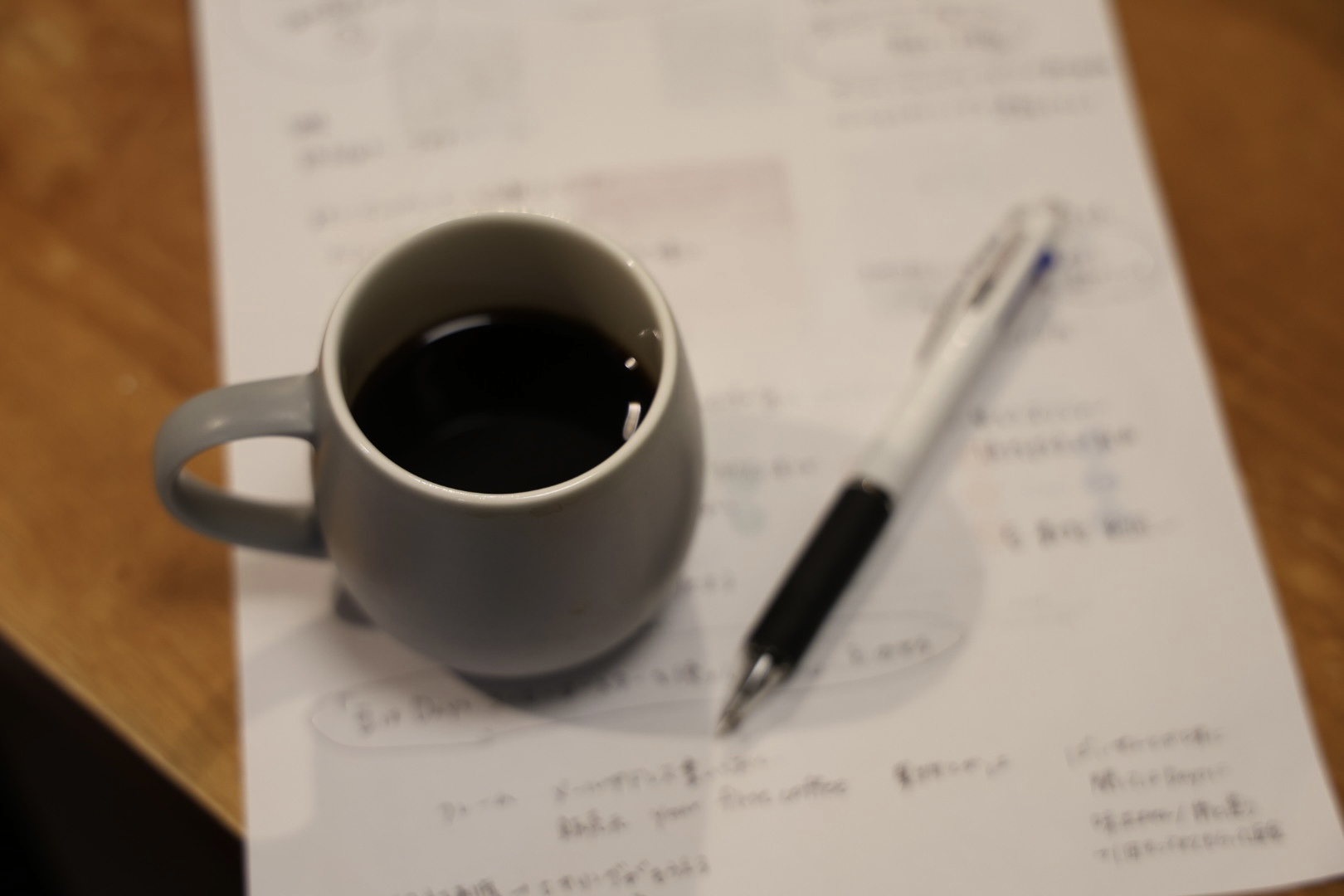

コメント